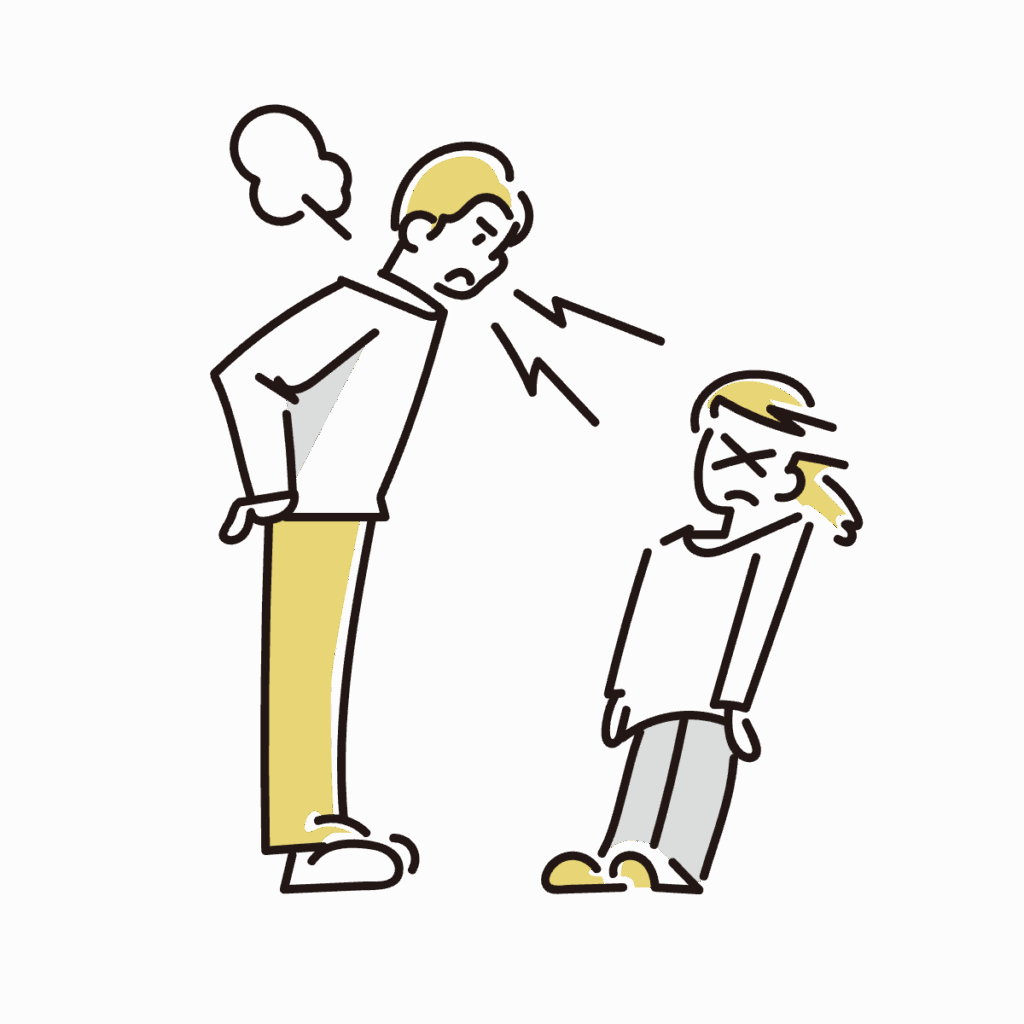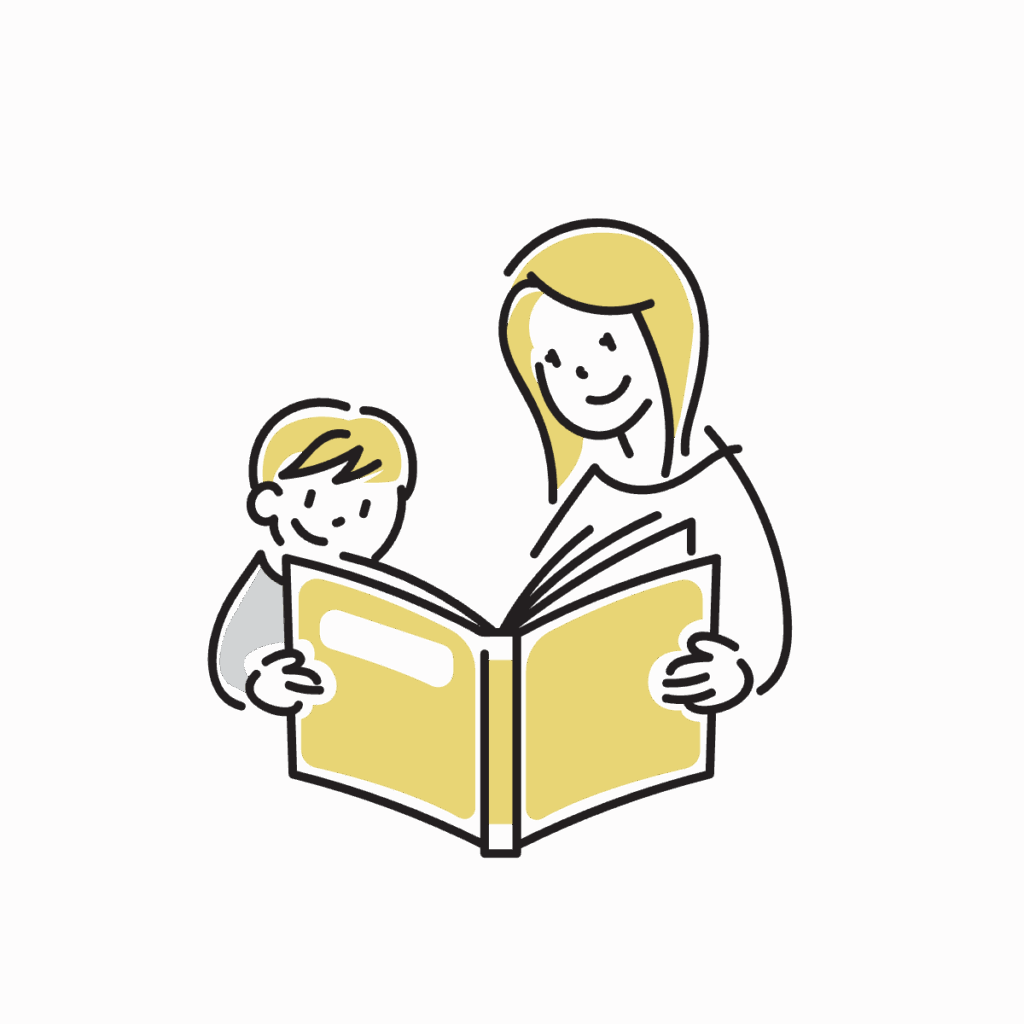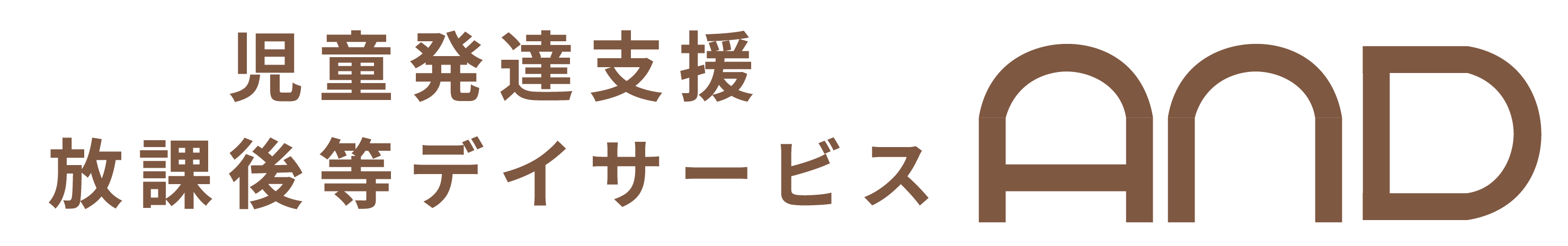支援員 伊澤しおり
「勉強ができるようになってほしいから」
「外で迷惑をかけないように」
「この子のためになると思ったから」
私は、息子にたくさんの“良かれと思って”をしてきました。
例えば、
ゲームをした後に宿題をすると言う息子に、「ダメ、先に宿題」と言い切ってしまったこと。
お気に入りだった小さなセーターを、本人に相談せずに片付けてしまったこと。
朝寝坊したら怒ること。
好き嫌いをさせないこと。
給食の箸を用意していない事に怒ってしまうこと。
髪型を決めること。
心配だから、あれこれ聞いてしまうこと。
何か問題が起こりそうな気がするから、行動を制限すること。
それは全部、心配だったり、効率を考えたり、この子が苦労しないように、と“やさしさ”から出た行動でした。
しかし、保育士養成学校に通い始め、さらに「あんど」と出会い。この環境の中で「子ども主体」とは何か、と日々考える機会が増えました。
そして“本人のため”と思って行うことが、実は本人の意思を無視している場合がある――という考え方を学びました。
そこから、私の中で静かな振り返りが始まりました。
「誰のために、それをしているんだろう?」
「それ、本当に“子どものため”なんだろうか?」
気づいたのは、私自身が幼い頃に“押し付けられて嫌だったこと”を、
今度は親という立場になって、知らず知らずに息子にしていないか。
決して支配するつもりはなかったけれど、その「良かれ」は、私自身の不安や安心のためだったのかもしれない、と。
親の「正しさ」と、子どもの「選ぶ力」は、ときにぶつかる。
でも今の私は、「子ども主体」という言葉の意味を、日々考え続けています。
失敗も、遠回りも、子どもにとっては必要な経験。
そこを、大人が先回りしすぎることで、子どもから「自分で考える力」を奪っていないだろうか。
皆さんにも、そんな経験…ありませんか?