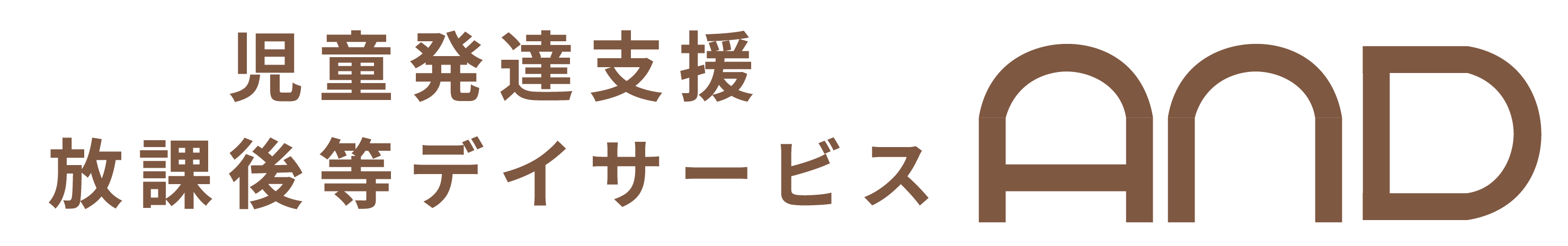二宮 昌枝
あちらこちらから聞こえてくる子どもたちの声が、夏休みの始まりを知らせてくれています。
一学期を終えた安堵感と夏休みのワクワク感でいっぱいの表情がキラキラ輝いています。子どもたちにはワクワク心おどる日々ですが、保護者の方たちには……
今回は、「家庭生活と子どもの役割について」考えてみたいと思います。
子どもたちが最初に所属する社会はおそらく家庭です。家庭は自分の居場所、生活の場です。また、助け合いを学ぶ場でもあると思います。毎日家族が楽しく暮らすために子どもたちと一緒に考えて役割を任せてみることも長い休みだからこそできることではないかと思います。
子どもに役割を任せる時には、まずは一緒にやってあげてほしいと思います。
学校では、「かかり活動」としていろいろな役割を分担して行っていますので、「おうちのかかり活動」にすることで、子どもに分かりやすく役割を意識させることができるかもしれません。
例えば、「かたづけかかり」として、自分の使ったものは、元あった場所に戻すことから始めたりすると、結果的に家族の負担が減り、助けていることにつながっていることを実感しやすくなるのではないでしょうか。
「人は一つのことを習得するのに100回程度の練習が必要である」と聞いたことがあります。夏休みのような長期の休みから始めると、長続きしやすく、子ども自身にとっても家族の助けになっていることが実感しやすくなります。秋ごろには自信をもって「かかり活動」=役割を行う姿が見られそうですね。
また、子どもたちには、役割が、どれだけ役に立っているかを感謝の言葉と一緒に伝えてほしいと思います。おうちの人からの「ありがとう」や「やってくれてとっても助かっているよ」などの言葉がけが、確実に子どもたちの励みにつながり、自分のかかり活動が家族を助けていることへの確かな認識につながっていくと思います。
子どもたちにとって、家族から認められたこれらの経験が、たくましく育っていくための大切な栄養になっていきます。